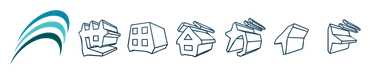世田谷区立郷土資料館は、東京都内では初の公立地域博物館として、1964(昭和39)年9月10日に開館しました。東京五輪の開幕ちょうど1カ月前の時期であり、翌年からは「日本の歴史」が刊行が始まったことによる歴史ブームが訪れた時期でもありました。
世田谷代官屋敷の敷地内にあり、区制30周年事業の一環として建てられました。土地は、一般財団法人大場代官屋敷保存会から無償貸与を受け、設計は、1959年竣工の世田谷区役所・区民会館も担当した前川國男氏によるものです。
収蔵資料が増加したことに伴って、1987(昭和62)年に新館が増築されています。
施設の老朽化などから、2022年4月から2023年7月にかけて休館し、大規模な改修工事が行われました。この時には施設・設備の更新に合わせて、常設展示の内容もリニューアルされています。高さ4.8メールの土層柱状図の設置や、第二次世界大戦後から高度経済成長期までの展示スペースの拡大、民俗・美術コーナーや、手に取って学べる体験コーナーの新設などが行われています。
地上2階地下1階、3つの展示室
世田谷区立郷土資料館は、本館は地上2階、新館は地下1階、地上2階建てとなっています。本館と新館は2階の渡り廊下で繋がっており、本館1階に展示室1、本館2階に展示室2、新館2階に展示室3の3つの展示室があります。
常設展示は、展示室1の旧石器から始まり、順路に沿って時代が進むようになっており、展示室2は縄文、弥生、古墳、古代、中世、大場家、近世、近代と、世田谷の歴史が解説とパネル、展示品によって紹介されています。
新館側にある展示室3は、前述のリニューアル前は企画展示室として利用されていましたが、リニューアルにより「美術」「民俗」の常設展示が行われるようになりました。また以前と同様、特別展や企画展、季節展、ミニ展示、遺跡調査速報展などの開催場所ともなっており、企画展とその開催前後には、展示室3の常設展示は見学できなくなります。
元々農村地帯だった世田谷区には、代々続く旧家も多く、都内の他の地域と比べて関東大震災や第二次世界大戦での被害も少なかったことから、多くの歴史的資料が残されてきました。郷土資料館はそういった資料の収集・保管にも役立っています。
閲覧室や集会室も
本館1階には、区の歴史や文化に関する資料を閲覧出来る閲覧室も設置されており、世田谷区以外の自治体の刊行物も収蔵されています。
新館1階には、講習会や講座、小学校の社会科見学時などに利用される集会室も設置されています。郷土資料館が利用していない時間帯は、区の郷土・文化・文化財などに関する活動を行っている団体向けに、有償で貸し出されています。貸出を希望する場合には、郷土資料館で事前に団体登録が必要となります。
同じく新館1階にはビデオブースも設けられています。2つのビデオブースでは、区の歴史や文化などに関する30本の作品が閲覧用に用意されています。うち20本は世田谷デジタルミュージアムでも公開されていますが、残りの10本は郷土資料館が作成したビデオとなり、このビデオブースでのみ閲覧可能です。
休館日は毎週月曜日と祝日
休館日は、毎週月曜日と祝日、年末年始(12月29日~1月3日)となり、月曜日が祝日に当たる場合は翌日も休館となります。開館時間は9時~16時30分です。
最寄り駅は、郷土資料館の北側にある東急世田谷線「上町」駅で、徒歩5分ほどの距離です。バスの場合は東急バス・小田急バスの「上町」が最寄りとなり、こちらも徒歩5分ほどの距離です。
郷土資料館には専用の駐車場はありませんが、世田谷代官屋敷の駐車場(無料)が空いていれば利用できます。代官屋敷の駐車場はボロ市通り沿いに入口があります。
| 住所: | 東京都世田谷区世田谷1-29-18 |
| 郵便番号: | 154-0017 |
| 鉄道1: | 東急世田谷線 上町駅 徒歩5分 |
| バス1: | 東急バス・小田急バス 上町駅 徒歩5分 |
| スポット名: | 世田谷区立郷土資料館 |
| よみがな: | せたがやくりつきょうどしりょうかん |
| 料金: | 無料 |
| 定休日: | 毎週月曜日、祝日(月曜日が祝日の場合はその翌日も)、年末年始(12月29日~1月3日) |
| 築年: | 1964年 |
| 駐車場: | 無し(※代官屋敷の駐車場が空いていれば利用可能)。 |

(c) Google Map